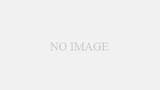私の母親は食の安全にとても関心が高く子供が口にする物は信頼できるものでなくてはいけないと考えて、おやつも含めてほとんどの物を手作りで作ってくれました。
外で作られたものはどのような材料から作られているか分からないので、自分は全て材料から作るんだ、という主義でした。
ジュースやジャムも季節の新鮮な果物を使って手作りしてくれていました。
買い物に出かけた時には、表示の見方を教えてくれて、産地や消費期限だけでなく、添加物などの気を付けなくてはいけない事まで細かく知ることができました。
おかげで私もそういった意識を小さなころから持つ事が出来、自分が母親になってから買い物や調理をする際に役に立っています。
食の安全を脅かすのは添加物などの化学的な物を始め、野菜や果物に残る残留農薬、狂牛病などの家畜の病気などさまざまな物があります。
決して日本国内で製造されていれば安心出来るというわけではありませんが、私はなるべく国内産の物を選ぶようにしています。
日本の基準が高い事も安心材料の一つですし、地産地消を進める事が国産の割合を高め、農家を守ることに繋がると思うからです。
私たち消費者が安ければよいと考えて安易に外国産の物を買うようになると、スーパーも外国産の物を並べるようになります。
国産のものにこだわる姿勢を一人一人が消費活動を通して示していく事が、意思表示だと思うので割高で合っても国産の物を買うよう心がけています。
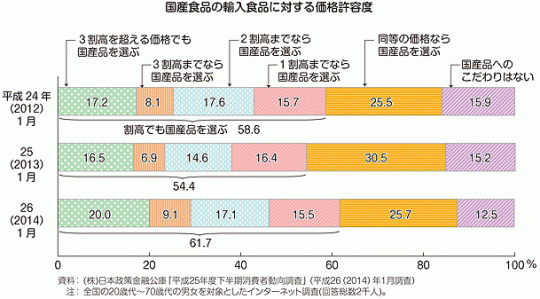
地産地消を応援して行くために、私は農協の直売所も良く利用しています。
虫食いのある野菜もありますが、兼業など規模が小さくても地元で畑を続けている人を応援したいからです。
大規模な農家を経営するのは大変でも、土日に兼業でちょこっと野菜作りをする人が増えてくれるのは頼もしいものです。
最近では全てが国産の物を使っているレストランなども増えてきました。
とても良い動きだと思います。
国産だということは消費者にとっては大切な選択ポイントです。
この動きが、小さな小売店やレストランだけにとどまらず、大手のチェーン店やショッピングモールなどの大きなスーパーにも広がって欲しいです。
野菜や肉類までいろいろな自給率が上がっていき、国産の市場が拡大していけば、安心して口にできる物を供給してくれる人が増えて行ってくれます。
そのような良い循環が出来上がる事が、将来を担っていく子供たちのためにもなります。
食の安全で大切なのが、砂糖や油など長期的に大量に取ると健康を害する事がはっきりとしている物とどう付き合っていくかという事です。
私は子供のおやつまで手作りする余裕がないので、つい、買って与えてしまいがちなのですが、ジュースなどにはどのくらいの砂糖が入っているかといった例をみるとぞっとします。
清涼飲料水にはスティックシュガーがかるく10本以上入っている事がほとんどです。
果汁なら、飲むヨーグルトなら、と少しでもましな物を選ぼうと考えたつもりでしたが、どんなに減らそうとしても飲み物を甘いものにしたらそれだけで一日の摂取量の目安を軽く超えてしまいます。
かといって、お茶やお水だけしか与えないようにするのも少しかわいそうな気がしてそこまでできません。
責めて、飲む機会を減らしたり、飲む量を減らすために小さな紙パックジュースを選んだりするように心がけています。
また、トランス脂肪酸が多く含まれている油で揚げたものや、原材料にそういったものが含まれている物は日常的に口にしないように気を付けています。
日本は基準が厳しいと思っていますが、諸外国では禁止されたり、WHOが勧告を出しているのにまだ日本では規制が不十分な物も結構あります。
そういった情報を、自分に届くのを待つのではなく、自分から積極的に収集する姿勢も必要なんだと思います。
子供の肥満や成人病などが社会問題になっていますが、それらは先天的な原因でないものは親の責任が非常に大きいです。
大人であれば、自分で気を付けて選ぶ事ができますが、子供は親の選んだ物を口にして育ちます。
親が子供の健康に責任を持って口にする物を選んでいかなくてはいけません。
どのような物を口にするとどのような影響があるとか、砂糖は一日にこのくらいまでとっても良い、塩分はこのくらいにした方が良い、という事を教得る必要もあります。
昔のように飢えで苦しむ事がなくなった現代は、飽食の時代と言われていますが、それが健康に悪影響を及ぼしているというのはとても皮肉な事です。
美味しいものが世の中にあふれている今では、健康や安全ばかり気にしていては楽しくないとも思いますが、普段から安全な物を口にするように心がけておけば、たまにはご褒美で、ちょっと体に良くはないけれど美味しい物を楽しむ事も出来るようになります。
家庭の台所を預かる私達一人一人が安全な物を求める姿勢をきちんと持って、食について考え、知識を深める事が大切です。
パッケージ業者の先駆けである朋和産業も食の安全を大きなテーマに挙げてます。